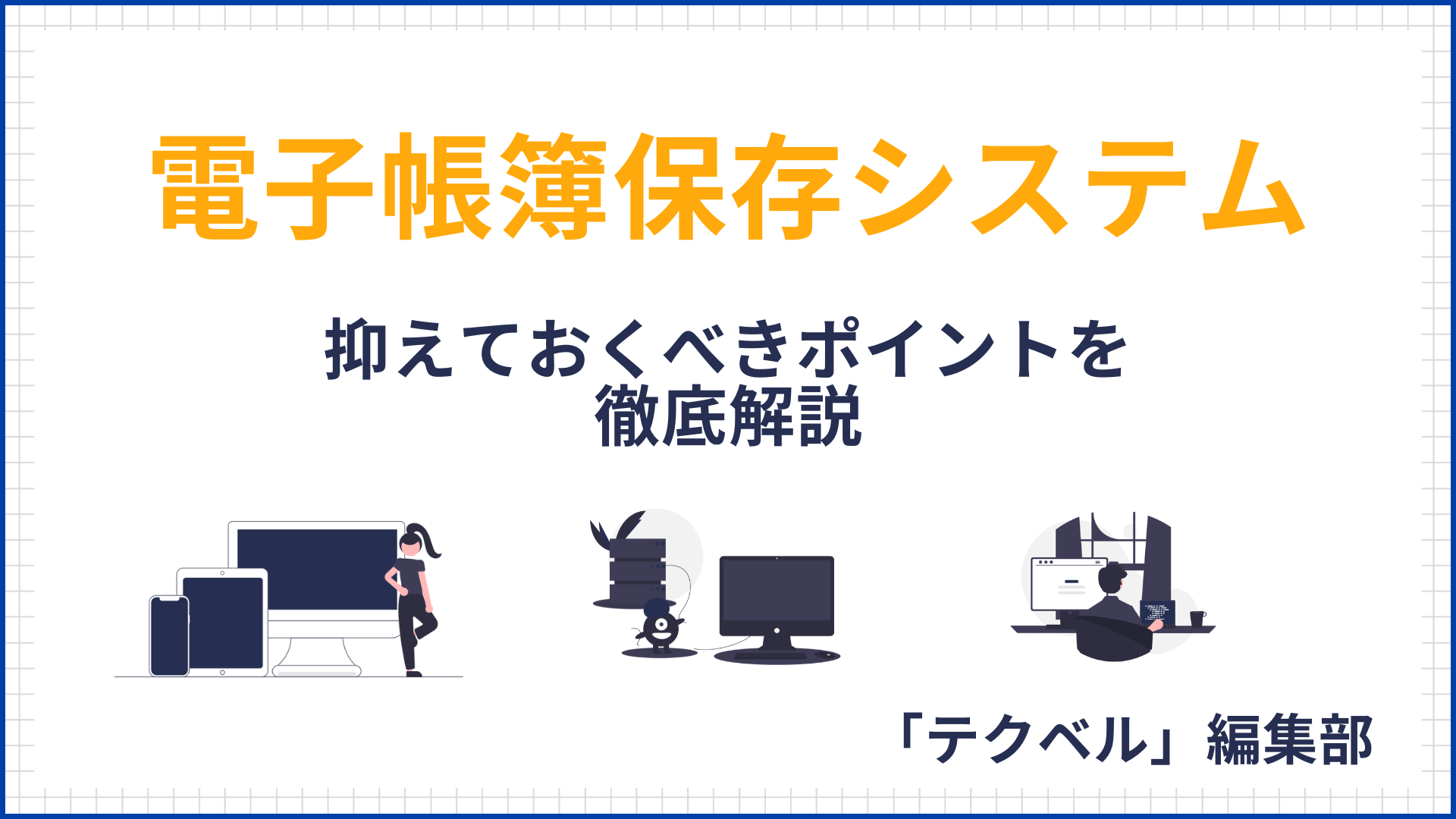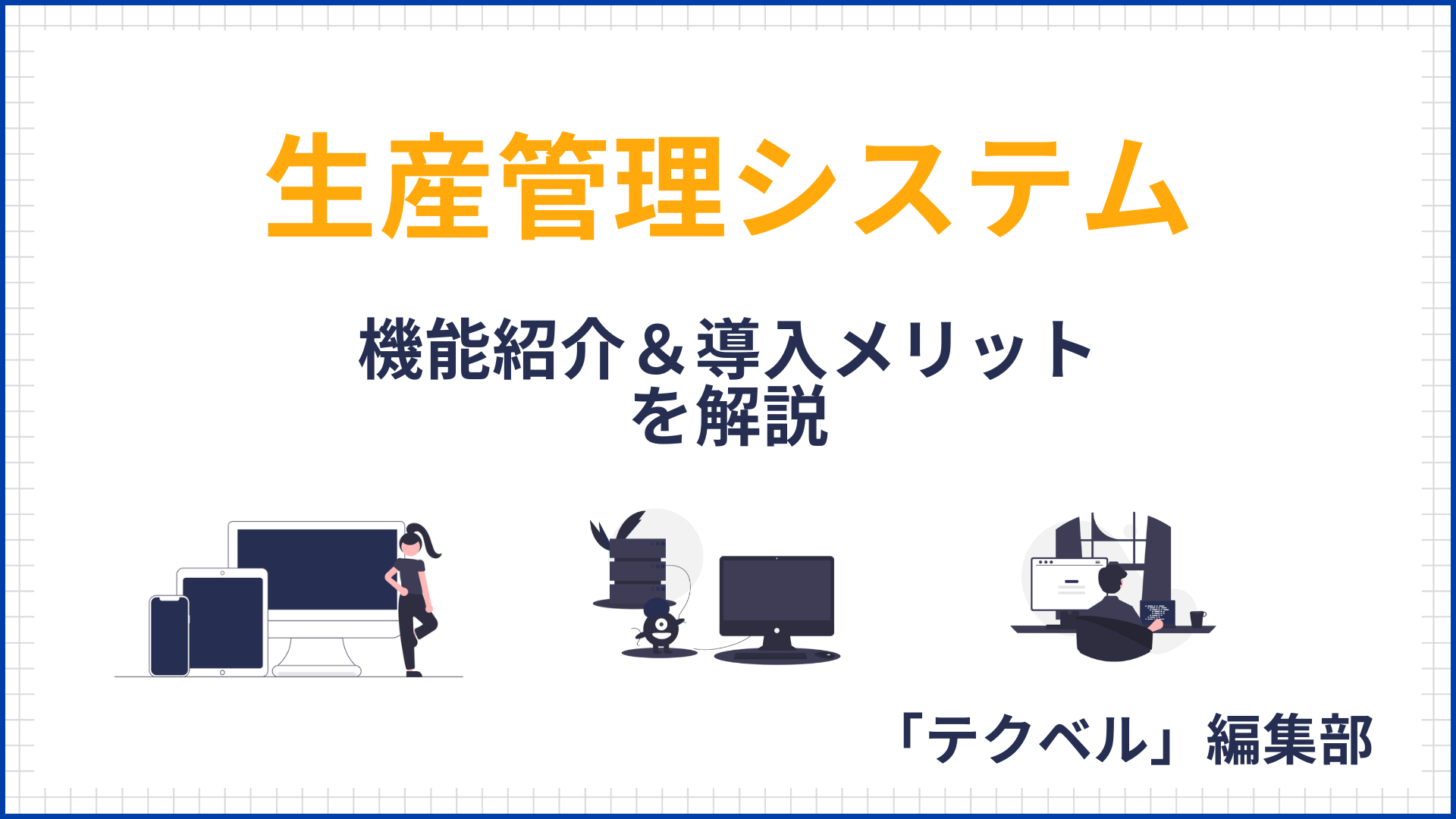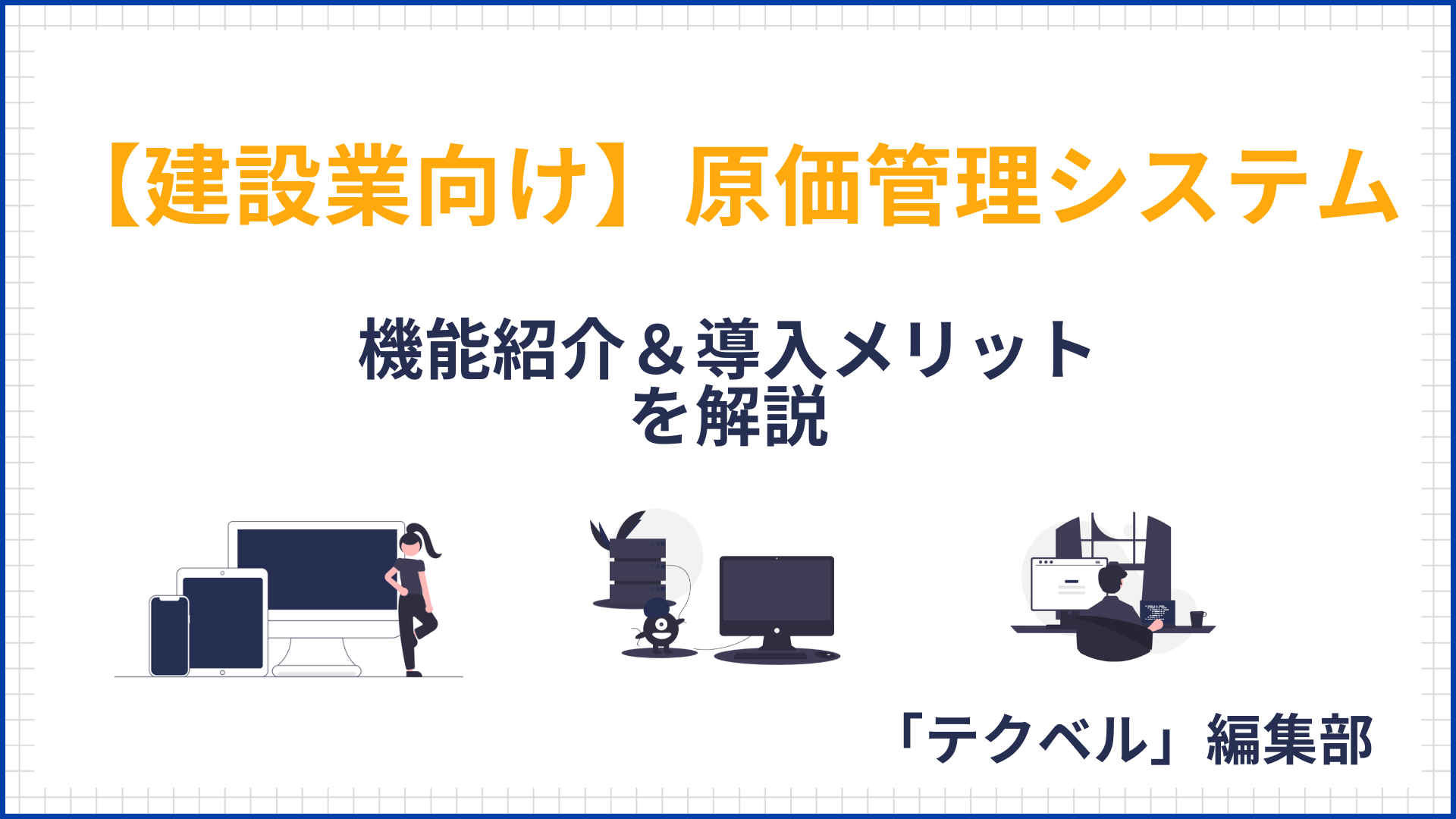目次
電子帳簿保存法のすべてを解説!2024年からの対応ポイントをわかりやすく解説
2024年1月より、電子帳簿保存法の改正が施行され、電子取引データの電子保存が完全義務化されました。従来、紙ベースで管理していた企業にとって、大きな変化です。本記事では、電子帳簿保存法の基礎知識から最新情報、そして2024年からの対応ポイントまで、わかりやすく解説します。導入を検討している企業にとって役立つ内容となっていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、1998年に施行された法律で、税務関係帳簿・書類を電子データで保存することを認める法律です。企業が帳簿や書類を電子データとして保存する際に、どのような要件を満たすべきか、またどのような手続きが必要かなどが定められています。
電子帳簿保存法は、経理業務の効率化、ペーパーレス化、コスト削減などに役立ちます。近年は、働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進など、社会全体でデジタル化が進んでいるため、電子帳簿保存法の重要性はますます高まっています。
電子帳簿保存法の改正内容
電子帳簿保存法は、社会情勢の変化に合わせて何度も改正が行われてきました。2022年1月には、大幅な改正が行われ、多くの企業に大きな影響を与えています。
改正のポイントは、以下のとおりです。
1. 事前承認制度の廃止
従来の電子帳簿保存法では、電子帳簿等保存やスキャナ保存を行うためには、事前に税務署長の承認を得る必要がありました。しかし、2022年1月からの改正により、この事前承認制度が廃止されました。
この改正により、事業者は、いつでも準備が整ったタイミングで電子保存を開始できるようになりました。
2. 電子取引における電子データ保存の義務化
電子取引は、注文書、契約書、請求書、領収書など、取引関係書類を電子データでやりとりすることを指します。
従来の電子帳簿保存法では、電子取引を行った場合でも、紙に出力して保存することが認められていました。しかし、2022年1月の改正により、電子取引の書類はデータで保存することが原則となり、紙に印刷して保存することは認められなくなりました。
3. 罰則規定の強化
電子帳簿保存法の改正では、電子データの記録事項に関する改ざん、隠ぺいなどの不正行為があった場合、罰則が強化されました。
スキャナ保存や電子取引データ保存において、不正行為を行った場合、その不正によって生じた申告漏れなどの税額に対して、重加算税が10%加重されます。
4. 検索機能要件等の緩和
電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引データ保存のいずれも、従来は複数の検索条件でデータを検索する機能が必要でしたが、2022年1月の改正によって検索要件が緩和されました。
電子帳簿等保存の検索機能に関しては、優良電子帳簿の要件を満たしている場合は、ダウンロード要件のみで検索機能は不要となりました。
スキャナ保存と電子取引データ保存の検索要件は、「取引年月日」「取引金額」「取引先」という3つの条件で検索できる状態であれば、それ以外の条件を満たさなくても問題ありません。
ただし、税務職員からダウンロードの求めに応じられるようにしておく必要はあります。
5. スキャナ保存のタイムスタンプ要件緩和
従来、スキャナ保存では、書類をスキャンして画像データにした後、概ね3営業日以内にタイムスタンプを付与しなければいけませんでした。しかし、改正により、タイムスタンプの付与期間は最長2か月と7営業日以内に延長されました。
また、データの改ざんができないシステムや、改ざんや削除を行った際にその履歴が残るシステムを利用する場合には、タイムスタンプの付与自体が省略できるようになりました。
6. スキャナ保存の確認要件廃止
スキャナ保存を行う際、従来は、読み取った画像データが書類の原本と同一であることを、社内の複数人で確認したり、定期的に検査を行ったりする必要がありました。しかし、改正により、複数人による確認と定期的な検査が不要になりました。
電子帳簿保存法に対応するメリット
電子帳簿保存法に対応することで、さまざまなメリットがあります。
1. 省スペース化
従来、紙で書類を保管するには、多くのスペースが必要でした。しかし、電子帳簿保存法に対応することで、書類を電子データとして保存できるため、物理的な保管スペースを大幅に削減できます。
2. コスト削減
紙の書類を扱うには、紙代、印刷代、インク代、ファイル代、保管スペースの賃料など、多くのコストがかかります。電子帳簿保存法に対応することで、これらのコストを削減できます。
3. 業務効率化
電子データで書類を管理することで、紙の書類を探したり、コピーしたり、ファイリングしたりといった手間を省くことができます。また、検索機能を活用することで、必要な書類を簡単に探し出すことができるため、業務の効率化が期待できます。
4. セキュリティ強化
紙の書類は、紛失や盗難、改ざんのリスクがあります。しかし、電子データで管理することで、アクセス権限を制限したり、改ざん防止機能を導入したりすることで、セキュリティを強化できます。
また、災害などのリスクにも対応できます。
5. 環境負荷の低減
紙の書類を減らすことで、紙の原料となる木材の使用量を減らし、CO2排出量削減につながります。環境負荷の低減にも貢献できます。
電子帳簿保存法への対応のポイント
電子帳簿保存法への対応は、企業にとって大きな課題です。しかし、適切な手順を踏めば、スムーズに移行できます。
1. 対象書類の確認
電子帳簿保存法の対象となるのは、国税関係の帳簿・書類、電子取引書類です。
まずは、自社でどのような書類をどのように取り扱っているのかを把握しましょう。
2. 保存方法の決定
電子帳簿保存法には、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つの制度があります。
自社の業務内容や規模などを考慮して、適切な保存方法を決定しましょう。
3. システムの選定と導入
電子帳簿保存法に対応したシステムの導入を検討しましょう。
システムを導入することで、データの保存、管理、検索を効率的に行うことができます。
電子帳簿保存法に対応した会計ソフトやクラウドサービスなどを活用すれば、さらに業務を効率化できます。
4. 規程類の整備
電子帳簿保存法に対応するための規程類を整備しましょう。
具体的には、下記のような規程を整備することが考えられます。
* 電子帳簿保存に関する社内規程
* スキャナ保存に関する社内規程
* 電子取引データ保存に関する事務処理規程
* データ管理に関する規程
5. 従業員への周知
電子帳簿保存法への対応について、従業員への周知徹底が必要です。
新しい業務フローやシステムの使用方法などを、しっかりと説明しましょう。
2024年からの対応例と注意点
2024年1月からは、電子取引データを電子データで保存することが義務化されました。
1. 電子取引の確認
電子取引とは、電子メール、インターネット、EDIなど、電子的にデータをやりとりする取引を指します。
自社ではどのような電子取引が行われているかを確認しましょう。
2. 電子取引データの保存方法の選択
電子取引データの保存には、下記4つの方法があります。
- タイムスタンプが付与されたデータを受領
- データに速やかにタイムスタンプを付与
- データの訂正・削除の履歴が残るシステムまたは訂正・削除ができないシステムを利用
- 訂正削除の防止に関する事務処理規程を整備・運用
自社の状況に合わせて適切な方法を選択しましょう。
3. データの保存場所の決定
電子取引データを保存する場所は、自社のサーバやクラウドサービスなど、さまざまな方法があります。
データのセキュリティやアクセス権限などを考慮して、適切な保存場所を決定しましょう。
4. 業務フローの見直し
電子取引データを保存するにあたって、従来の業務フローを見直す必要があります。
特に、承認フローやデータの受け渡し方法などを明確化しましょう。
5. 従業員への周知
電子取引データ保存の義務化について、従業員への周知徹底が必要です。
システムの使用方法や、データの保存方法などを説明しましょう。
6. 猶予措置の活用
2024年1月以降、電子取引データ保存の要件を満たすことが困難な場合、猶予措置が適用される可能性があります。
猶予措置を受けるためには、税務調査時に電子取引データのダウンロードの求めに応じられるようにしておく必要があります。
まとめ
2024年1月からは、電子帳簿保存法における電子取引のデータ保存が完全義務化されました。
電子帳簿保存法への対応は、企業にとって避けて通れない課題ですが、適切な準備と対応をしておくことで、業務の効率化やコスト削減、セキュリティ強化など、多くのメリットが期待できます。
本記事を参考にして、自社にとって最適な対応方法を検討していきましょう。