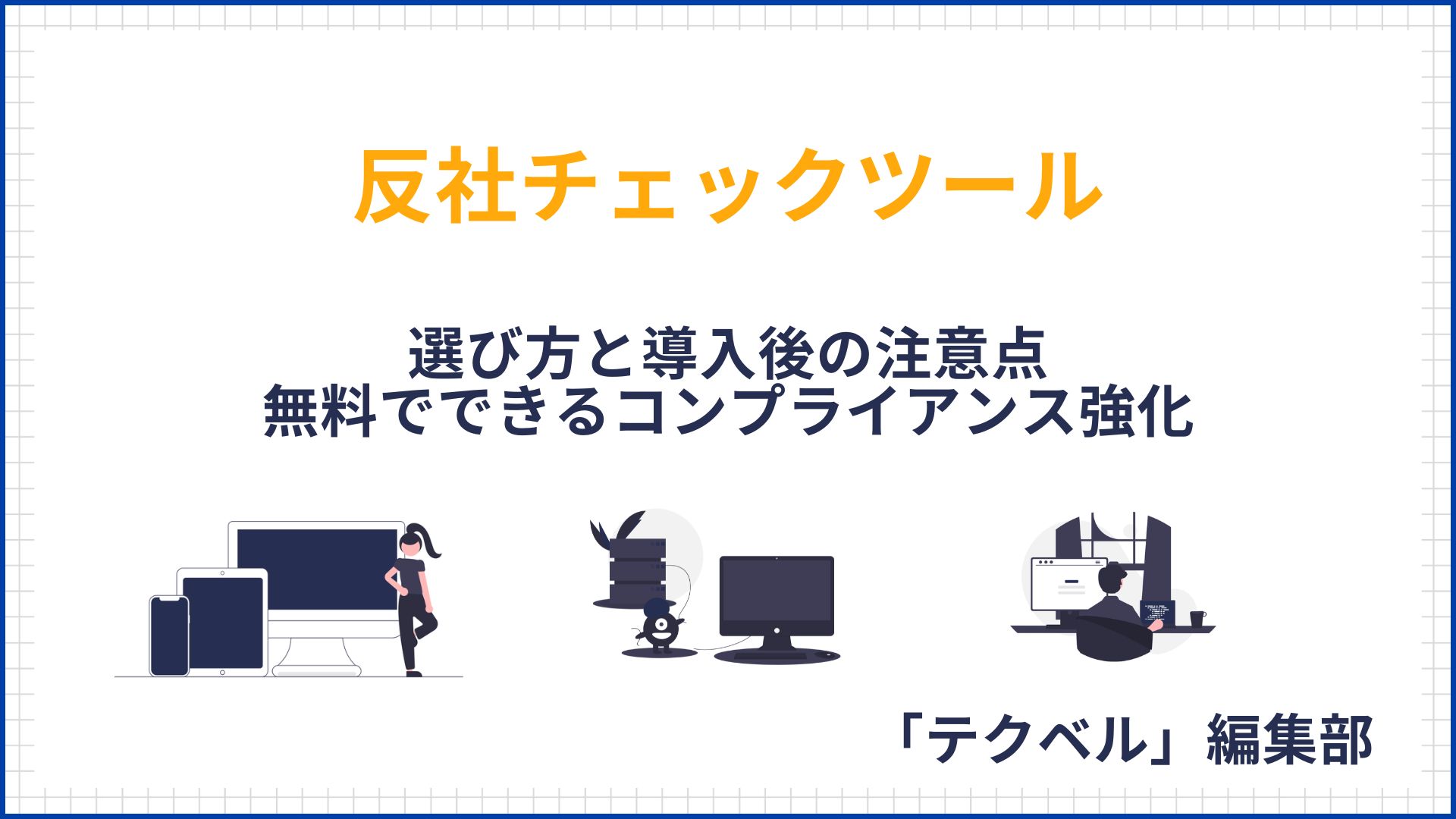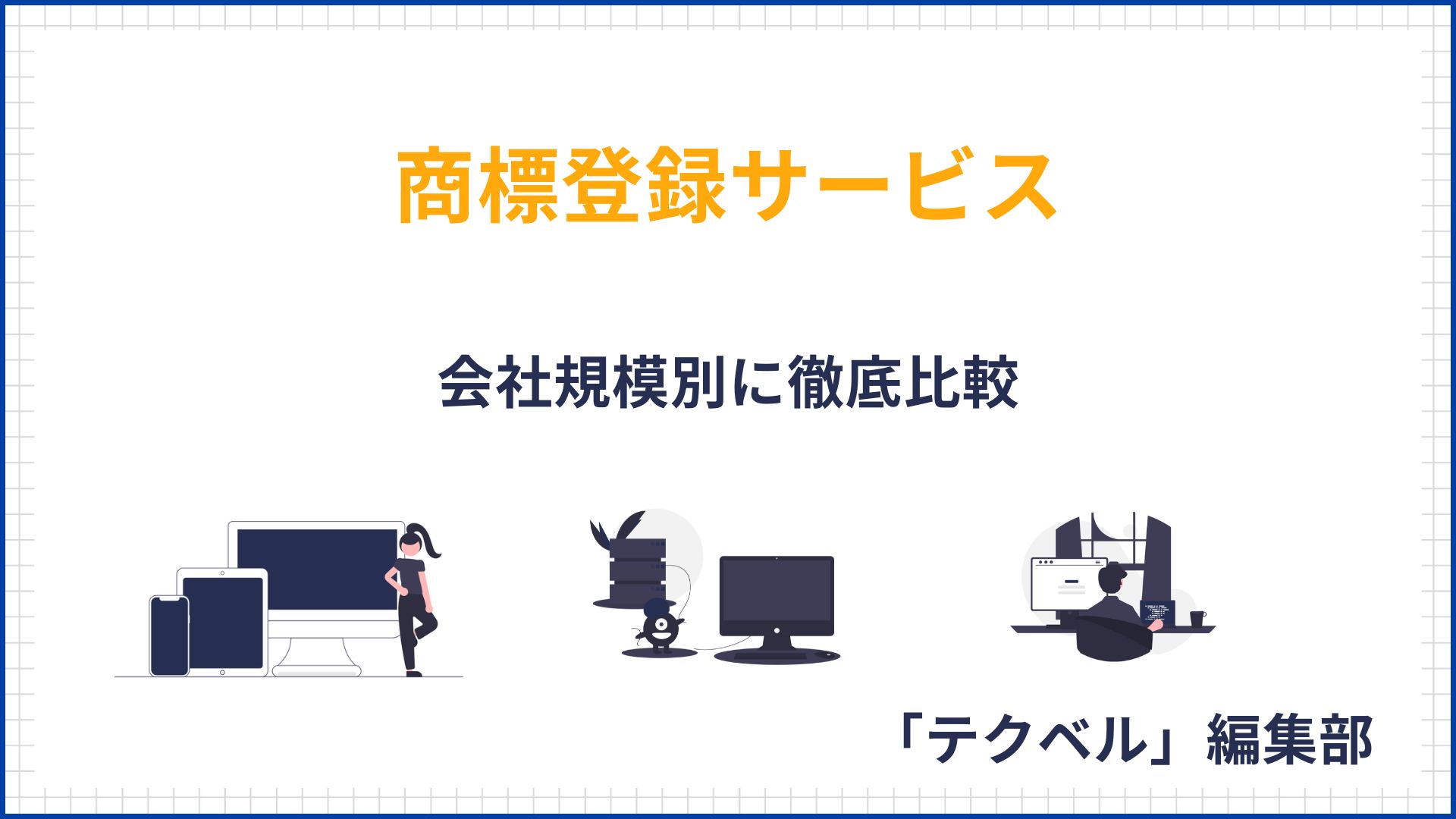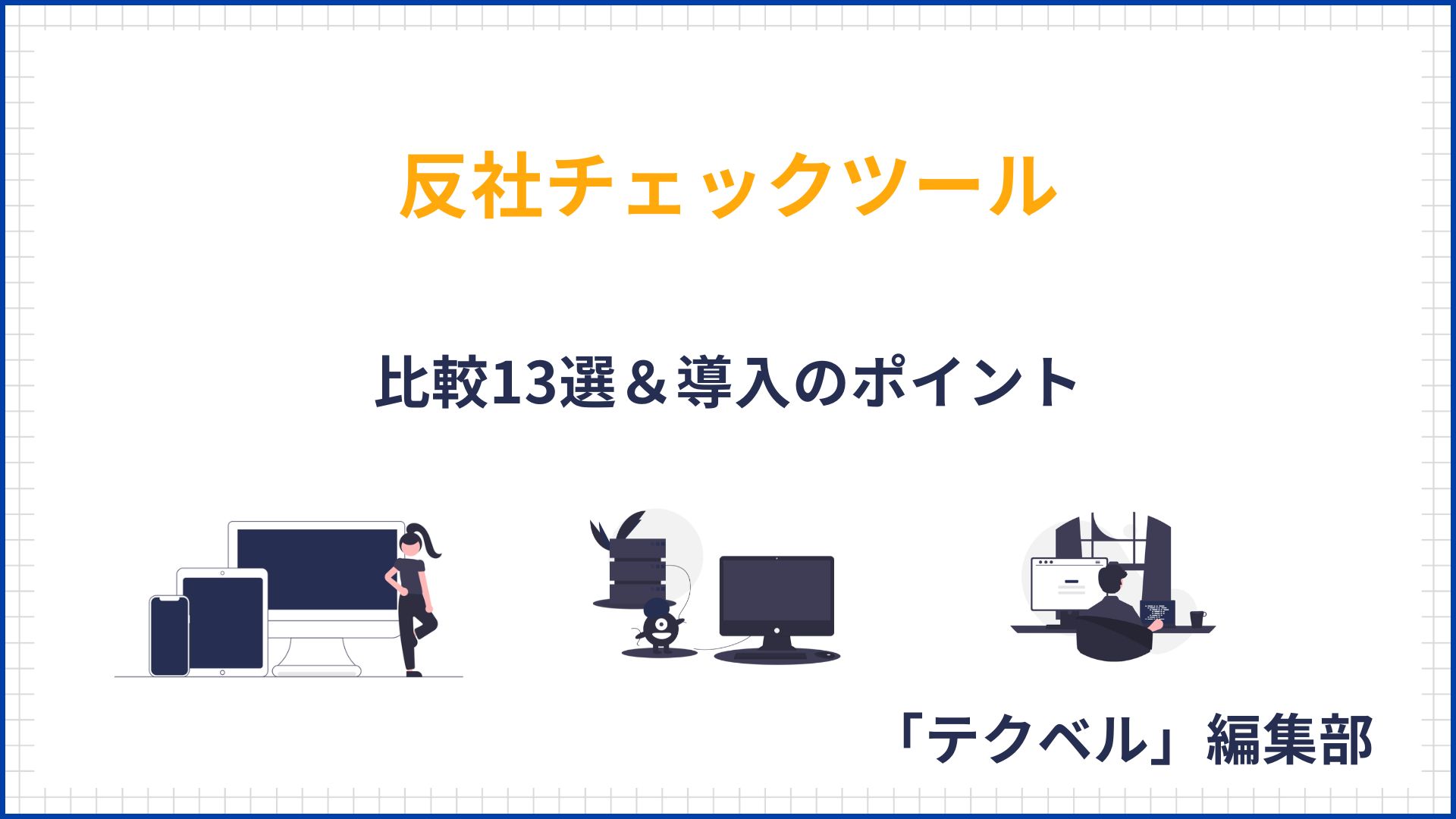目次
反社チェックツール導入でコンプライアンス強化!選び方から導入後の注意点まで解説
近年、企業にとって「反社チェック」は必須の作業となっています。取引先や従業員が反社会的勢力と関係を持っていれば、企業のイメージダウンや法的リスク、さらには不当要求や暴力といった深刻な被害に繋がりかねません。
しかし、反社チェックは手作業で行うと膨大な時間と労力を要します。そこで注目されているのが、反社チェックツールです。反社チェックツールを導入すれば、効率的に反社チェックを実施し、企業のコンプライアンス強化とリスク管理を実現できます。
本記事では、反社チェックツールの選び方から導入後の注意点まで解説します。これから反社チェックツールを導入しようと考えている企業担当者様は、ぜひ参考にしてください。
目次
- 反社チェックツールとは?
- 反社チェックの必要性
- 反社チェックツールのメリットとデメリット
- 反社チェックツールを選ぶポイント
- 情報源の信頼性
- 情報の確実性
- 情報の網羅性
- 調査の効率性
- データの更新頻度
- コストパフォーマンス
- その他自社のニーズ
- 反社チェックツールおすすめ5選
- RoboRoboコンプライアンスチェック
- アラームボックス パワーサーチ
- RISK EYES
- RiskAnalyze
- minuku
- 反社チェックツール導入のメリット
- リスクの軽減
- 反社チェック業務の効率化
- 社会的信用を守れる
- 反社チェックツール導入の注意点
- ツールだけに頼り切らない
- 定期的に反社チェックを行う
- 情報漏洩のリスクとプライバシー保護の対策
- 反社チェックツール導入後の対応
- 反社との取引を断ったら嫌がらせを受けたりしないの?
- 反社と判明した場合の社内フロー
- 反社と判明した場合の伝え方・断り方
- 自社のオフィスに反社が来訪したときの対応方法
- まとめ
1. 反社チェックツールとは?
反社チェックツールとは、取引先や従業員が反社会的勢力と関係を持っているかどうかを調査するためのツールです。企業が反社会的勢力との関係を遮断し、安全な取引を行うために利用されています。
1.1 反社チェックの必要性
反社チェックは、企業のコンプライアンス強化や、社会からの信用の維持などの目的で実施されます。近年、反社と関わることで生じるリスクは、企業の存続に関わる重大な問題として認識されています。
反社チェックが必要な理由を具体的に見ていきましょう。
- 政府指針・条例で定められている:反社チェックは、企業が反社会的勢力との関係を絶つために必須です。全国の都道府県や各自治体では『暴力団排除条例』に、企業の努力義務として反社会的勢力との関係遮断のための、誓約書、契約書の条項などの対策が規定されています。
- 万一反社との関係が明らかになれば、企業存続のリスクがある:反社と取引をしたり、利益供与をすることは、暴対法や『暴力団排除条例』などで、企業に義務づけられた罰則もある違反行為です。犯罪収益であると知って金銭を授受した場合などでも結果は同じです。企業が反社勢力と関係があるとみなされれば、企業イメージは失墜し、取引先からも事業継続を敬遠されるおそれがあります。法令違反により罰則や行政処分を受け、入札停止、許認可の取り消し、金融取引や資金調達の中止など、事業存続も危ぶまれる事態に陥るかもしれません。
- 上場企業や経済団体・業界団体の基準に定められている:上場企業には上場基準や証券取引所の規則、金融商品取引法などの法令を守る義務があります。新規上場を目指す企業なら、反社会的勢力との関係がないことの証明や、反社チェック体制の整備がなければ、上場審査は通りません。上場企業が改善報告書の提出や、最悪の場合には上場廃止になることもありえます。経済団体や業界団体でも、同様に反社会的勢力との関係遮断を定めた基準、規則を設けていることが多いでしょう。
- 反社からの不当要求をされるリスク、企業存続の危機を回避するためには、期間の限定なく継続的に反社チェックをすることが不可欠です。
1.2 反社チェックツールのメリットとデメリット
反社チェックツールには、自社で反社チェックを行うよりも多くのメリットがあります。
メリット
- リスクの軽減: 反社と取引をしてしまうリスクを軽減できます。
- 反社チェック業務の効率化: 手作業で行うよりも、短時間で多くの情報を調べられます。
- 社会的信用を守れる: 反社と取引していると思われてしまうリスクを軽減できます。
- コスト削減: 人件費や外注費などのコスト削減が見込めます。
デメリット
- 完璧なチェックはできない: ツールだけでは、すべての情報を網羅することはできません。
- 費用がかかる: ツールによって料金体系は異なりますが、無料のものもあれば高額なものもあります。
- 定期的なチェックが必要: 一度のチェックで安心するのではなく、定期的にチェックする必要があります。
2. 反社チェックツールを選ぶポイント
反社チェックツールは、さまざまなベンダーから提供されています。自社のニーズに合ったツールを選ぶために、以下のポイントを参考に検討しましょう。
- 情報源の信頼性: 警察や国、自治体など公的機関の情報源は信頼性が高いですが、ネット上の匿名掲示板やSNSなどの情報は信頼性が低い場合があります。
- 情報の確実性: 複数の情報源から同じ情報が得られるか、特定の情報源にだけ依存していないかなどを確認しましょう。
- 情報の網羅性: 収集可能な情報をどれだけ網羅的に収集できるか、新聞社のデータベースやメディア・公官庁の情報をどれだけカバーしているかを確認しましょう。
- 調査の効率性: ノイズスクリーニング機能やAPI連携機能など、調査を効率的に行うための機能が充実しているかを確認しましょう。
- データの更新頻度: データベースの更新頻度が適切か確認しましょう。最新の情報にアップデートされていない場合、誤った情報に基づいた判断をしてしまう可能性があります。
- コストパフォーマンス: 自社の予算と求める機能が合致しているかを確認しましょう。高機能なツールは高額になる傾向があります。
- その他の自社のニーズ: これまでの6つのポイント以外にも、自社が求める機能やサポート体制が充実しているかなどを確認しましょう。
3. 反社チェックツールおすすめ5選
自社のニーズや予算に合った反社チェックツールを選ぶために、ここではおすすめの5つのツールを紹介します。
3.1 RoboRoboコンプライアンスチェック
どんなニーズに合致するか
- コストパフォーマンスの良い反社チェックを実施したい
- 上場企業にも対応できる高水準の反社チェックを行いたい
- 情報を偏りなく網羅的に収集・調査したい
- 常に最新の情報源から情報収集したい
- 反社リスク管理システムを初めて導入してみたい
特徴
- AIにより反社チェック業務を自動化したクラウド型の反社管理システム
- 監修には、ネット証券大手のSBI証券が携わっており、上場企業にも十分対応しうる品質
- 3000社以上の中小・上場企業に導入され、99.5%もの企業がリピート
- 情報源は、インターネット情報(一般的なWeb記事から業界専門メディア、官公庁情報、SNS、ブログなど)から地方紙・全国紙の各種新聞記事まで網羅
- 簡単操作でマニュアル不要
- 高精度のスクリーニング
- 従量課金制、単価100円から利用可能
- 初期費用ゼロ円、無料お試しプランあり
3.2 アラームボックス パワーサーチ
どんなニーズに合致するか
- できるだけ費用をかけずに高い効果の反社チェックを実施したい
- 独自データベースなどの情報源で高精度の調査を実施したい
- 初めて導入するツールを検討している
特徴
- ワンコイン反社チェックと呼ばれる専門調査機関の独自情報源の照会が可能
- インターネット上の情報(ブログやSNSなどの風評も含む)や新聞記事データベースといった公知情報を参照した調査も可能
- 独自の情報源に基づく深度ある調査が期待できる
- 情報源の信頼性が高い
- リスク情報を過去3年分遡及して調べることができる
- 調査の効率性が高い
- AIがリスクレベルを3段階にランク付け
- API連携可能
- 30日間の無料トライアル期間あり
3.3 RISK EYES
どんなニーズに合致するか
- 信頼性や網羅性のある情報源を参照した調査を実施したい
- 国外の反社リスクにも備えた情報収集や調査を実施したい
特徴
- 新聞記事からインターネット検索情報(SNS、掲示板、ネットニュース記事、ブログなど)まで広範な調査が可能
- 各国の公的機関の制裁リストも検索可能
- 情報源の信頼性・確実性・網羅性が高い
- AIが関連度の高い情報をグルーピング・除外
- API連携可能
- 自社の顧客管理システムとの連携で、営業部門などとの迅速な共有が可能
- 無料お試し版あり
3.4 RiskAnalyze
どんなニーズに合致するか
- 独自データベースの情報の信頼性と鮮度の両方を重視したい
- 海外リスクにも対応したツールを使いたい
- 調査からレポートの作成、証跡保存まで一括で管理したい
特徴
- 国内1,000媒体以上のメディア・官公庁の配信情報を1時間おきに自動収集
- 最新の情報に強く、信頼性が高い
- CSVデータのアップロードや、API連携で、1つ1つ情報を入力する手間を削減
- AIによる無関係な情報のスクリーニング、記事の要約、リスク判定により、効率的な反社チェックを実現
- 調査からレポートの作成、証跡保存まで一括管理
- レポート作成は1件につき0.4秒で完了
- 海外情報240カ国に対応
3.5 minuku
どんなニーズに合致するか
- 独自の情報源による調査にも力を入れて反社チェックを実施したい
- 全国の1,000サイトという広範な情報源を参照したい
- 情報の網羅性を特に重視したい
特徴
- 反社会勢力の定義を統一した上での調査を実施
- 各社であいまいになりがちな部分を明確にした調査
- 全国のメディア約1000サイトの公知情報(新聞各社のデータベースやインターネット情報など)を独自のクローラで情報収集
- 独自の情報網で企業の定性情報も収集
- データベースの情報源は、ローカルな情報、新聞や雑誌、1000以上のサイトから収集した公知情報の両方
4. 反社チェックツール導入のメリット
反社チェックツールを導入することで、多くのメリットが得られます。
- リスクの軽減反社チェックツールを活用することで、取引先との取引や関係を安全に行うことができます。反社と取引をしてしまうと、不当要求を受けたり、暴力的な脅迫や犯罪行為に巻き込まれたりするリスクがあります。反社チェックツールによって、取引相手が反社会的勢力との関係を持っていたり、犯罪歴があるかどうかなどを確認できます。
- 反社チェック業務の効率化反社チェックツールは、反社チェックに必要な情報を自動的に収集・分析する機能を持っています。これにより、人手に頼っていた反社チェック業務の負担を大幅に軽減できます。従来は、新聞や雑誌、インターネットなどの情報を手作業で検索し、膨大なデータの中から必要な情報を見つけ出す必要がありました。反社チェックツールを使えば、これらの作業を自動化し、時間と労力を大幅に節約できます。
- 社会的信用を守れる反社チェックツールを用いることで、企業の社会的信用を守ることができます。取引先に反社会的勢力が含まれていると、自社も同勢力と見なされる可能性があり、社会的信用が失墜し、他の企業との取引が困難になるケースも少なくありません。
- 業務効率化反社チェックツールは、単に反社チェック業務の効率化だけでなく、企業全体の業務効率化にも貢献します。
- 時間短縮: チェックにかかる時間が短縮されることで、従業員は他の重要な業務に集中できるようになります。
- 人材活用: 反社チェック業務に割いていた人材を、より効果的な業務に充てることができます。
- コスト削減: 人件費や外注費などのコスト削減が期待できます。
5. 反社チェックツール導入の注意点
反社チェックツールは、導入する前に注意すべき点がいくつかあります。ツールだけに頼り切らない、定期的にチェックを行う、情報漏洩のリスクとプライバシー保護の対策など、具体的な注意点を見ていきましょう。
- ツールだけに頼り切らない反社チェックツールは、反社チェックを効率的に行うためのツールですが、万能ではありません。ツールは、膨大な情報を収集し、スクリーニングしてくれますが、判断は最終的に人間が行わなければなりません。
ツールが提供する情報が常に正確かつ最新であるとは限らないため、人の目で情報を確認し、ツールが誤って判断していないか、最新の情報が反映されているかなどを確認することが重要です。
- 定期的に反社チェックを行う反社チェックは、一度行えば終わりではありません。取引開始後も、定期的にチェックを行うようにしましょう。
企業は、取引相手が反社会的勢力と関係を持ち始める可能性や、新たなリスク要因が生まれる可能性も考慮する必要があります。定期的なチェックは、リスクの早期発見と対処を可能にし、潜在的なトラブル防止につながります。
- 情報漏洩のリスクとプライバシー保護の対策反社チェックツールは、企業のコンプライアンス強化に役立つ一方で、個人情報や企業情報の漏洩リスクが伴います。特に、データ管理体制が不十分な場合、プライバシー侵害や情報漏洩が発生しやすく、企業の信用に深刻なダメージを与え、顧客からの信頼を失いかねません。
反社チェックツールは、取引先や従業員の個人情報を扱うため、プライバシー侵害や情報漏洩のリスクが存在します。情報収集の範囲や利用目的については、必ず本人の同意が必要です。情報を適切に管理し、不正アクセスや流出を防ぐ体制を構築しなければなりません。情報漏洩が発生した場合、企業の信用失墜だけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。
反社チェックツールの導入にあたっては、プライバシー保護の観点からも慎重な対応が求められます。個人情報保護法などの法令を遵守し、適切な情報管理体制を構築することが重要です。導入前にツールのプライバシーポリシーを確認し、自社の情報管理体制との整合性を確認することで、ツールが収集した情報の不正利用や漏洩を防ぎ、企業の信頼性を確保できます。
6. 反社チェックツール導入後の対応
反社チェックツールを導入した後も、適切な対応をすることが重要です。
- 反社との取引を断ったら嫌がらせを受けたりしないの?反社チェックで取引相手が反社会的勢力と判明した場合でも、嫌がらせなどの報復を恐れて関係をもち続けてしまう、というケースがあります。しかし実際には、適切な対処をすれば、反社会的勢力からの嫌がらせを受けることはほとんどありません。
反社会的勢力が嫌がらせをしてこない理由は、きちんと対応すれば嫌がらせを受けることはほとんどない、きちんと対応すれば相手は「この会社は面倒だ」と諦める、仮に嫌がらせ行為に及んだ場合には直ちに警察に通報するなどがあります。
- 反社と判明した場合の社内フロー相手が反社と判明した場合には、慌てず適切に対処する必要があります。社内で対応方法が共有・徹底されていない場合には、担当者ごとに対応が異なってしまい、その隙につけこまれてしまうリスクが生じます。
具体的なフローとしては、上司に相談する、社内で情報を共有する、詳細な反社チェックを行う、弁護士に相談するなどがあります。
- 反社と判明した場合の伝え方・断り方反社会的勢力との関係を遮断するにあたって、例えば「反社チェックに引っかかったから」などと正直に理由を伝える必要はありません。このような伝え方をしてしまうと、「言いがかりだ、証拠を出せ」、「名誉棄損だ」などと騒がれ、問題が大きくなってしまうリスクが生じます。
具体的な断り方については、①契約締結前と②契約締結後で方法が異なるため、順に説明します。いずれの場合も、反社会的勢力が食い下がってくることが想定されますが、粘り強く同じ内容を繰り返し伝え、不用意に他の情報を伝えないようにしましょう。
- 契約締結前の断り方: 法律上、「誰と・どのような内容の契約を・どのような形式で・結ぶかどうか」は両当事者の自由とされています(契約自由の原則/参照:民法521条 – e-gov法令検索)。そのため契約締結前であれば、基本的には一方的に契約の締結を拒否することが可能です。 具体的には、単に「上司の決裁が下りなかった」等の理由をつけて契約の締結を拒否すればよく、上司に会わせろと言われた場合も「社内規定により許されない」と言えば足ります。
- 契約締結後の断り方: 契約締結後の場合、基本的に、一方的に契約を解消することはできません。 したがって、契約書に包括的な契約解除条項が設けられていればその条項に従い、条項がない場合には相手方との合意によって契約を解除する必要があります。 しかし、契約締結時に反社会的勢力排除条項が設けられている場合には、その条項に違反したことを理由として、一方的に契約を解除できます。 もちろん反社会的勢力排除条項がある場合にも具体的に伝える必要はなく、単に「契約違反があったため」と説明すれば十分です。
- 自社のオフィスに反社が来訪したときの対応方法契約の締結拒否、および契約解除の意思表示は、口頭で行うのではなく、必ず書面で行いましょう。これは、口頭でのやり取りを行うと些細な言い間違いを大げさに取り上げたり、威圧的な言動で契約の締結・継続を取り付けようとしてくるためです。 仮に直接会わせろとしつこく要求された場合、録音機材などの設置が容易で、心理的優位にも立てる自社での対応を行うようにしましょう。 オフィスでの具体的な対応方法については、後ほど詳しく紹介します!
7. まとめ
この記事では、反社チェックツールの導入方法、選び方、導入後の注意点などを解説しました。
反社チェックは、企業にとって非常に重要です。しかし、自社で反社チェックを行うのは、時間と労力を要する作業です。反社チェックツールを導入することで、業務効率を向上させ、企業のコンプライアンス強化とリスク管理を実現できます。
反社チェックツールを導入する際は、自社のニーズに合ったツールを選び、適切な運用体制を構築することが重要です。
反社チェックツール導入を検討されている企業担当者様は、ぜひこの記事を参考にして、自社にとって最適なツールを選び、安全なビジネス環境を構築してください。